10/30(金)コンペティション『カランダールの雪』の上映後、ムスタファ・カラ監督、ネルミン・アイテキンさん(プロデューサー)、ビラル・セルトさん(脚本)、ハイダル・シシマンさん(俳優)をお迎えし、Q&A が行われました。⇒作品詳細
ムスタファ・カラ監督(以下、監督):長い映画を観てくださり誠にありがとうございました。気に入っていただけたのであればよいのですが。私も日本の監督の作品をたくさん拝見しました。そして、今回は私たちの方が皆さまにこのストーリーをお届けすることになりました。
ハイダル・シシマンさん(以下、シシマンさん):このように長い映画を観たあとに残っていただき、ありがとうございます。あるストーリーに届けようと、表現しようと、私たちもできる限りのことをしました。世界の遠い端のところからやってきて皆さんにお届けし、そして観てくださって大変感謝しております。願わくばまたお会いできる機会がありますように。
ビラル・セルトさん(以下、セルトさん):この『カランダールの雪』はシナリオの段階から制作まで、非常に難しい過程を経ました。また、観賞にあたっても特別な関心、興味、辛抱強さがいる作品です。それを観てくださいまして誠にありがとうございました。
ネルミン・アイテキンさん:皆さん来てくださってありがとうございました。他に言うことはありません。
Q:「カランダール」という言葉は、字幕では「新年」と訳されていましたが、トルコで使われている暦と関係があるんですか。
セルトさん:「カランダール」は確かに新年という意味ですが、それだけでなく、もっと特別な意味を持った言葉です。新年の時に行われる伝統的な行事についても「カランダール」という言葉が使われます。
Q:映画製作もハイリスク・ハイリターンだと思いますが、監督も主人公の一攫千金を夢みるというところに共感されているのでしょうか。
監督:私もメフメットに似ているんだろうと思います。ただ、メフメットはそこで物質的な見返りだけを求めているわけではありません。同時に、幸福であったり、自らを存在ならしめることを求めています。彼はそのことに成功した。それは、皆さんも私も人生では同じなのだと思います。
Q:滋賀県から来ました。シナリオで、最後にあのシーンを持ってきたのはどうしてですか。
セルトさん:遠くから来たお客様を悲しませない内容にしました!(笑)私達のことわざに「探したものは見つからない、見つけたものを探したことになるんだ」というのがあります。
Q:主演の方は、駄目な男を演じて楽しかったのでしょうか。
シシマンさん:これだけ頑張っても、まだメフメットは駄目な男に見えるんですね。でも、彼には成功したことがあります。メフメットは自然や家族とずっと格闘状態を続けているんですが、決してひるんだり諦めたりすることはありません。そういった信念の象徴なのです。決して諦めることはしないで、結末がどうなるかを知らずに戦い続ける事ができる男なのです。ですから、怠け者なわけではありません。
Q:違うエンディングを考えたことはあるのですか。
セルトさん:多くの映画は、関係者の間で戦いながら製作をするわけですが、この作品も素案の段階からするとずいぶん違いが出てきました。それでも、色々な点でお互いの合意に達しました。ラストシーンについてもいろいろと意見がありまして、どちらががいいか話し合い、最後にはご覧いただいた内容のほうがいいということになり、これをひとつの希望の光として、ラストシーンに置こうということになりました。これが、結果でした。
監督:少し補足します。ラストシーンをあのようにした理由は、単にストーリー上のことでもなく、メフメットのためでもありません。それはおそらく、皆様方のため、あるいは私たち自身のために、そこに希望の門を開けておこうとしたのです。開けておくのが良いのではないかと。そのためだったのだと思っています。
Q:英語で”Chasing Rainbow”(虹を捕まえる)としている言葉を、日本語字幕では「ふらふらする」と訳されています。”Chasing Rainbow”はトルコ語では元々どういう意味の言葉を使っているのでしょうか。
監督:奥さんが喋った言葉ですね。それは、無駄なこと、やっても何もならないことのために、色々やることです。というのは、女性の方が男性よりも具体的なことをもっと求めるじゃありませんか。トルコのことわざのようなものでして、英語に訳すとご覧になった言葉になります。英語にも”Chasing Rainbow”という表現があります。
Q:撮影の技術が素晴らしく、映像の美しさに感動しました。ほとんどの場面が自然光で撮影されていると思います。夜の場面に関しても、ひょっとしたら薪の光だけで撮影されているのでしょうか。その辺りの撮影の方法について教えてください。
監督:この映画製作では、俳優の演技についても、ストーリーについても、できるだけリアリティを大事にして表現しようとしました。リアリティをキャッチする方法を取ったのです。撮影上の技術については、こういう風にしたいと願った瞬間をキャッチした時に、私達は撮影をしたのです。例えば、夕方のシーンであれば実際に夕方を、また夜であればその時、その雰囲気を出せるような光が出て来るのを待って撮影しました。現在の技術を使って、プロフェッショナルなロケセットを組み、必要なものすべてを現地のロケーションに置きました。このような映画の場合、例えわずかであっても人工的なもの、あるいは自然に反するものを置いてしまうと、自然やその組織的なものを破壊してしまうことになります。なので、できるだけそういうことは避けたのです。
Q:この作品を4年間かけて撮られたということですが、この先もこのようなドキュメンタリーとフィクションをミックスした作風で撮られていくのか、あるいは今までのようにドキュメンタリー作品を作っていくのか、監督の今後にとても興味があります。
監督:まず今回の作品にあたっては、俳優、シナリオ、様々なアクセサリー、ロケーションのセットに至るまで、なるべくドキュメンタリーに近い、リアリティを反映させたものに近づけさせるようにしました。それが私たちの目的でもありました。しかしながら、リアリティを反映させながらもすべては実際にはフィクションなんです。ドキュメンタリー風のリアリティをキャッチすることによって、この作風が強くなると私たちは思ったのです。
次のプロジェクトについては別のストーリーを考えていまして、それは都会のできごとです。しかし作品の目的はやはり同じで、そこで生きる人々の人生、どんなふうに生きているか、どんなことを感じているか、なるべくリアリティを持って、キャッチして、そこに近づいていく、という風に考えています。
最後に
監督:今回、この映画によって、実は私たちは皆さん自身のストーリーを、皆さんのことを理解しようとしたのです。そして、皆さんの方は、私たちを知る機会をこの映画で得ていただけたのであれば幸いです。また東京で皆さんと一同に会して、こういったおしゃべりを共にしたいと思います。ありがとうございました!
2015.11.16
[イベントレポート]
「ラストシーンは皆様のため、あるいは私たち自身のために、希望の門を開けておこうとしました」コンペティション『カランダールの雪』-10/30(金):Q&A
Tweet
左から ネルミン・アイテキンさん(プロデューサー)、ビラル・セルトさん(脚本)、ハイダル・シシマンさん(俳優)、ムスタファ・カラ監督|©2015 TIFF

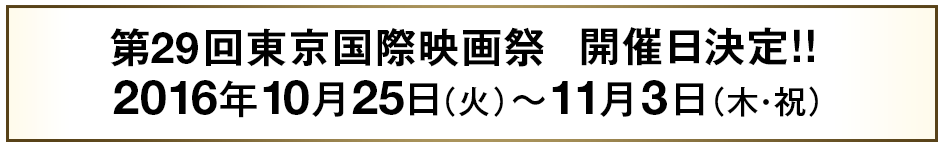
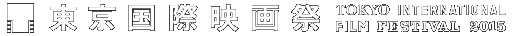


















 Check
Check






