10/29(木)コンペティション『ルクリ』の上映後、ヴェイコ・オウンプー監督、ユハン・ウルフサクさん(俳優)、ミルテル・ポフラさん(女優)、ティーナ・サヴィさん(プロデューサー)をお迎えし、Q&A が行われました。⇒作品詳細
ヴェイコ・オウンプー監督(以下、監督):今日はお越しいただきまして誠にありがとうござまいす。日本に来てから数日経ちますが、未だに興奮冷めやらぬというか、びっくりすることだらけで本当に驚いています。
ユハン・ウルフサクさん(以下、ウルフサクさん):皆さんこんばんは。一昨日着いたということで少し時差ぼけもあり、またこれだけ多くの方に観に来ていただいて少しばかり圧倒されています。非常に温かく歓迎していただき、大変嬉しいです。
ミルテル・ポフラさん(以下、ミルテルさん):こうやって日本までやって来られて大変光栄に思います。東京国際映画祭の皆さんと交流してみて、こんなにフレンドリーなところはないんじゃないかと思っています。
ティーナ・サヴィさん(以下、サヴィさん):今日はお招きいただきありがとうございます。日本の皆様のおもてなしに本当に感動しております。
Q:ストレートにおうかがいします。「ルクリ」とは何なのでしょうか。
監督:「ルクリ」というのは、実は僕が住んでいる家の近くにある森の名前で、その森は聖地なんです。キリスト教がやってくる前から聖なる土地だったのですが、これには様々な伝説があります。地元の人々は決してそこには行かない、いわゆる踏み込んではならないゾーンになっていて、つまりこの映画において、我々の知識の限界を超えたところにある、未知なるものの象徴と思ってください。
Q:後半の森のシーン、あれが「ルクリ」の森ということでしょうか。
監督:あそこは「ルクリ」の森の非常に近くにある場所でして、なかなか奥深いところなので、機材を運んだり、そこに行くまでが大変でした。
Q:この映画では、隔絶されたコミュニティに唯一、旧来的な宗教観が残っていて、それが戦争や外から来たものによって崩壊していくのを描いていると思います。監督の中にはもともと、そういう信仰のようなものがあって今作を作られたのでしょうか。
監督:まず、この映画で何を描かんとしているかという話から始めます。おっしゃっていることと非常に似ている部分はあるんですが、「脅威にさらされた人間たちの性とは」といことを描こうとしています。人間性、あるいはその人間たちの宗教観、そうしたものが瓦解しはじめるところを描くわけです。4人の主人公一人ひとりが変化を遂げていくわけですね。それぞれの信念であったり、信ずるものが崩れていくのです。ただ、これについて踏み込んで話すには時間が足りないので、本気で話すと一生かかるので、ここではこれ以上は語らないでおきます。
それから、自身の宗教観については、ちょっとプライベートなことなので皆様にはお話しできないのですが、「疑問に思うことはあります」とだけ申し上げておきましょう。
もう少し補足して説明すると、今まで別の劇場でQ&Aをしたり取材をしたりして一つ分かったことは、とにかく皆さん、混乱されているようだと。ただ僕はですね、すべてを把握できない、知らないというのはとても大事なことだと思っています。そういうわけでこういった新鮮なアプローチを取っているのですが、そもそも確固たる確信なく何かに意味を付するというのは、よろしくないことなのではないかと思っているわけですね。ですから、いわゆるお話が展開していくプロットという構造はあえて取りませんでした。プロットはたいてい三幕目には何か起こるというのがあらかた予想がついてしまうので、それではつまらない。ここではそのプロットという構造、あるいはそれに付随する意味をすべて削ぎ落として、ふるい落として、みなさんを分からない状態に落とし込んでみると。そういう志の映画でありました。人によってはうまく納得していただけた場合もあるし、そうではなかった場合もありました。
Q:俳優の二人はこのような状況の中、どの程度、自分が何をやっているか理解しながら演じられていたのでしょうか。脚本があったのか、あるいは状況設定だけ与えられて、その中で自由にやってくれと言われたのか。
ウルフサクさん:シーンによって様々なプロセス、やり方、アプローチがあって、例えば脚本があったりなかったり、あるいは脚本には書かれていたけれども削ってやってみたり、またあるいは脚本をそのまま使ったり、いろんなアプローチを取りました。中にはどう使われるのか、どこに向かっているのか分からないけれども、この台詞を言えというのがあったり。例えば、街が崩壊して彼女が号泣するシーンがありますが、あれはそれしか脚本に書いていないんですね。そこからは即興で、そういう意味では俳優として非常に充実した体験となりました。
ポフラさん:スケジュールが、何の日にどのシーンを撮るかというのが決まっておらず、とにかく4週間で撮り終えなければいけないということだけ決まっていました。なので、シーンによってはたっぷりと時間をかけましたし、例えば数週間前に撮ったけれども、ちょっと直さなければいけないシーンをもう1回撮り直すことが出来たり、こちらとしては非常にやりやすく、役に立つようなプロセスでした。また、お互いの信頼関係を築けるような作り方だったと思います。
Q:タイトルにシンボルのようなものを使っていますが、どのような意味があるのでしょうか?(会場にいた『フルコンタクト』の監督、ダビッド・フェルベークさんによる質問)
監督:これは聞かれなければ敢えて説明しようとは思わなかったんですが、聞かれたのでお答えします。あれはチベット仏教にちなむものでして、チベット仏教にある8つのシンボルのうちの1つです。「エンドレスノット」(直訳すると「無限の結び目」)という、サムサラ(輪廻転生)を表現しているものです。このコンセプトは個人的に原罪に通じるものだと思っていて、人間が今置かれている精神の状況というのは、どこかで何かが間違ってこうなっちゃったという状況なのだと思います。
Q:戦争の予感が漂うディストピア的な世界を描いていますが、直接的な契機として、ロシアのウクライナ侵攻というのがこの映画をつくるバックグラウンドにあったりするんでしょうか。
監督:まさにその通りです。影響はあります。おっしゃる通り、ちょうどロシアのクリミア半島の侵攻が一年半前にあり、戦争が我々にとって非常に身近な脅威となったわけです。その時に感じた不安がこの企画の原動力になっているというのはおっしゃる通りです。作っていくうちにもう少し根本的な問いが頭をもたげたんですが、そもそも戦(いくさ)というのはなんなのか、どうして人間はこうなったのか、おそらくは人間の心理だとか、精神が起因して、人はこうやって日々、戦争をしているんではないだろうか。その辺りを掘り下げる作業をしたいというのがありました。
また、制作においてもいろいろと実験したいというのがありまして、このプロジェクトは非常に限られて予算で、クラウドファウンディングに頼っている部分も多分にあります。皆さんノーギャラで参加してもらっているんですが、その収益はみんなで等分に分配するという話もしているんですね。そういう従来の映画づくりとは違う、より人間的な映画制作というのが出来るのではないかという志があって作ったものでもあります。
Q:ロシアのウクライナ侵攻の他に、この映画をつくる原動力となったものはありますか?
監督:日々疑問に感じていることに関していうと、このテーマでは戦などが描かれているわけですが、これは映画でなくとも人が日々、生きていく中でどうしても意識せざるを得ない、非常に普遍的なものではないかと思います。それに加えて言うならば、芸術形態としての映画というのは一体なんなのかということにも前から興味があったんですね。つまり、その構成要素とはなんなのかという疑問とか、従来からあるドラマツルギーとか、ドラマの構造ですよね。それを瓦解してみようという一つの試みでもありました。それと先程、記者会見でも申し上げましたが、みなさんをエンターテインしたいという気持ちはあるんですよ。
Q:劇中で流れるサム・クックの「ア・チェンジ・イズ・ゴナ・カム」がすごく映画に奥行きを与えていると思いました。あの曲は映画を撮る前から使おうと思っていたのでしょうか。
監督:僕はたいてい映画を作るときには、構想段階でいろんな楽曲をかき集めるんですね。撮影が終わるまでずっとそういう楽曲を聴いて、編集段階で「ああ、ここはこの曲だな」という風に決めていくわけです。半意識的にやっていることですね。ただこれは、今回はうまくいったと自分でも思っています。
Q:サム・クックが流れた時は椅子から転げ落ちるかと思いました。「いつかは世の中は変わるさ」という歌なのですが、ストレートすぎるが故に、この映画の最後だとちょっと皮肉もこもっているのではと感じます。
監督:普通にストレートに入れていますよ。ばかばかしいシンボルというか、分かりやすいシンボルというのが好きなんですよね、僕は。こういったものというのはやはり真実を宿すものでして、我々はちょっと、今はいささかシニカルになりすぎているのではないかと思うんですね。メッセージを受け取って、それそのものとして受け取れなくなってしまっている部分があるんじゃないかと。ただ、シンボルというものは、きちんと時間をかけて素直に向き合っていけば、そのメッセージというのはクリアに伝わってくるので、単純なメッセージであってもうまく伝わるというか、染み込んでくることはあると思うんです。
Q:映画の中で雲を映すシーンが何回か出てきて印象的でした。普段から雲を撮り貯めていらっしゃるのか、4週間の中でいい雲を撮ったのか、教えていただければと思います。
監督:本当にあらかじめ計画を練って撮ったわけではなくて、そういうことを言うのも恥ずかしいんですが、撮影が始まる前の企画段階でもあんまりものがなかったんですよ。お金もなかったし、時間もなかったので、撮り進めていくしかなかったんです。ということで、あの雲は撮影期間中に撮っています。編集段階で入れようということにしたんですが、一つは地上で繰り広げられる小さい人間ドラマから、少し視点を別のところへ移すという効果があるのと、もう一つには、そこで描いている世界をより広大なものにしていく効果があるのでないかと思います。
Q:演出上の質問です。前半はほとんど台詞がないですが、出演者に対して演技を要求していたのかしていなかったのか、どちらですか?
監督:私は撮影をする時に、このシーンはこうしたいという考えが割とはっきりしていて、このシーンではどういう情報を伝えたいのかとか、そういうのをあらかじめ決めているんですね。それをキャストのみなさんに説明し、無理強いすることもあります。が、大方はその役者に任せる場合が多いです。狡猾に役者をだましてノせてしまうこともあります。
Q:では役者のお二人におうかがいしますが、マニピュレイトされたり(操られたり)はしているんでしょうか。
ウルフサクさん:完全に操られていますが、監督をがっかりさせたくないので気づいていないふりをしていますよ。お互いにみんなそれぞれを操っています。
ポフラさん:脚本通りに台詞を言ったときもあれば、書かれた台詞を削ったこともあり、そしてそれを変えたりした時もありました。お互いに自由にディスカッションはできたので、例えば会話をどう変えていくのかとか、キャラクターやこのストーリーにとってのベストな選択肢はなんなのか、いろいろ話し合うことができました。例えば、キャンドルを持っているシーンがありますが、あれは脚本の中ではみんなでテーブルを囲んで会話をするという設定だったのが、撮影に入ってみたら、一人ずつキッチンの暗闇の中でモノローグをやる、こっちの方がうまくいくよね、という結論にいたり、そういう風に変えたりもしました。あのシーンを撮っているときも、監督がここではこういう台詞を言えとか、そういった指示がその場で出たこともありました。
ウルフサクさん:ちなみにいうと、あの家には実際に一緒に住んでいました。普通、映画の撮影って役者にそれぞれ自分のスペースというのがあって、メイクルームがあったりするわけですが、今回はメイクなどもなく、あったとしてもみんなそれぞれ、自分でやっていたので、完全に一緒に住んでいました。ということで、1つのまとまったフローというか、作業になったんです。制作チームのスタッフも同じ家の中の別室に住んでいたので、一つのとてもユニークなグループ体験となったというか、役者としても非常に面白い経験をさせてもらいました。
監督:前半部分の台詞がとても少ないのも意図的なものでして、つまり五感に訴えかけるような映画にしたかったので、そうすると脚本に書かれている台詞が非常にニセモノっぽいというか、ちょっと本物感がなかったんです。役者に言わせてもどことなく不自然だったので、できるだけリアルに描くために、あえてダイアログを削ぎ落としました。
Q:音楽の使い方がとてもユニークでした。音楽についてはどのような考え方を持っているのでしょうか。
監督:私はたぶん音楽を使いすぎることが多いんじゃないかと思います。というのは、失敗をごまかすのにいい方法なんでね(笑)。森の中のシーンの音楽は別の作曲家がついているんですが、これは僕も少し関わっていることでして、実際に僕も演奏なんかしたりもしています。
ウルフサクさん:後で聞いたんで、ぼくもびっくりしました(笑)
監督:作曲家も非常に気に入ってくれたみたいで、今度バンドでもやろうかと言ってくれました。なので、今度の来日はバンドを引き連れて、音楽でポストロックみたいなことをやってみるのもいいんじゃないかと思っています。
2015.11.16
[イベントレポート]
「次の来日ではバンドを引き連れて、音楽でポストロックみたいなことをやるのもいいなと思っています」コンペティション『ルクリ』-10/29(木):Q&A
Tweet
左から ティーナ・サヴィさん(プロデューサー)、ユハン・ウルフサクさん(俳優)、ミルテル・ポフラさん(女優)、ヴェイコ・オウンプー監督|©2015 TIFF

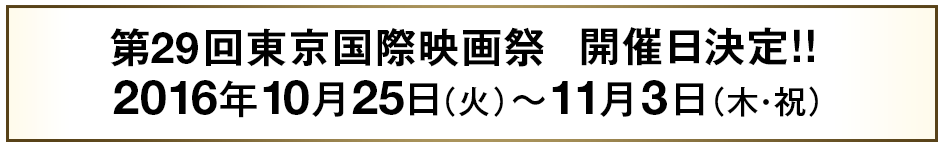
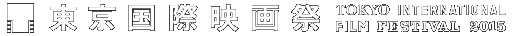


















 Check
Check






