10/30(金)アジアの未来『俳優 亀岡拓次』の上映後、横浜聡子監督をお迎えし、Q&Aが行われました。⇒作品詳細
横浜聡子監督(以下、監督):『俳優 亀岡拓次』を監督しました横浜聡子と申します。まず映画祭にお招き頂いて本当にありがとうございます。まだ上映2回目ということで、世に出たばかりの『俳優 亀岡拓次』ですが、作品について皆さんと対話できればなと思います。
Q:今回は安田顕さんを起用されています。最近はテレビで目にする機会も多いですが、もともとは演劇だった方のキャスティングですね。どのようなきっかけでそうなったのかをお聞かせ下さい。
監督:安田顕さんはあまり存じ上げませんでした。映画とかドラマで、まさに亀岡みたいで、この方見たことあるなっていうのはありました。プロデューサーに安田顕さんという俳優さんの存在をまず教えていただいて、そこから注目するようになりました。かなり個性的な役をやられる方だなと思っていまして、安田さん自信が何を考えてるのか分からないというか、怖さというのがすごくあるなと。自分を出さない感じ?まぁ私が勝手に思ったんですけど、ある種の闇の部分というか、何か抱えてる人なんだろうなという気配に惹かれました。それから亀岡拓次と安田さんというのは私の頭のなかでかなりリンクさせながら脚本を書いたりしていました。
Q:書いている段階で亀岡拓次=安田顕さんの顔みたいな感じですか?
監督:顔は浮かんでいました。あと安田さんが他の俳優と徹底的に違うのは、芸があるということだと思うんですよ。芸といったら失礼かもしれないんですが、映画のなかでもおならとかゲップをしてくださいって言うとすぐできるっていう。俳優だったら必ずできるという技じゃないと思うんですけどできるんですよ。それで私は安田さんの舞台を見に行ったんです。ヒッチコックの三十九階段という作品を原作にした舞台なんですけど、そこでミスターメモリーっていう、記憶術で生きている人間というか、自分の思考じゃなくて、人から記憶しろと言われたことしか頭の中にない、ある種の機械的な、壊れたロボットみたいな役を安田さんがやられていて。その時の動きが、喜劇俳優というかコメディアクションのように素晴らしい動きをされていて、この人はバスターキートンのような喜劇俳優なんだと強く感じました。それを亀岡でも是非取り入れたいなと。亀岡拓次はこの映画の喜劇俳優なんだというように、いつしか頭の中でリンクしていった瞬間はありましたね。
Q:工藤夕貴さんについてはいかがですか?
監督:工藤夕貴さんは2年前に私が地元の青森で撮った『りんご農家の少女』という作品に、主人公のお母さん役で出てくださって、それからのご縁です。女性マネージャーの藤井という役で今回は出演していただきました。
Q:個性的な方々の役柄を演出するにあたって、こういう感じでやってくださいというイメージは何かあったんでしょうか?
監督:この映画では4人の監督が出てくるんですが、いかにも映画監督っぽいビジュアルってあるじゃないですか。一般的にいう……本当に大御所ですと黒澤明監督とか。ディレクターチェアにどっかり座ってサングラスかけという、分かりやすい監督にしたくないなと思っていました。でも、山崎 努さんだけはご自分の中で、それまでご一緒されてきた映画監督のイメージがすごくあって、例えば「衣装の色を黄色にしたい」とか、山崎さんの中に確固たるイメージがあったので、なので山崎さんだけはいわゆる日本のベテラン監督というビジュアルからまず始めさせていただいたというか。強いご意思があったので、そこに面白く乗っかったという感じでした。
Q:亀岡が舞台に出たり、海外の監督のオーディションを受けたり、一人舞台をしたりというシーンがありますが、それは先ほどの話にあった舞台からの影響があるんでしょうか?
監督:安田さんの舞台を見てからという発想ではなく、原作にも「亀岡が海外監督のオーディションに呼ばれてホテルの一室で対面する」というシーンがありまして、そこから飛躍したいなと考えていました。映画で描いたあのオーディションのシーンは、監督がだいぶ遠くにいるという距離感とか、後ろの映画のスクリーンを背景に使いたいなとか、頭の中の画のイメージから発想されたシーンです。元々は、戦争の映画が背景に流れて、その手前で亀岡が右往左往するというシーンを脚本の最初の段階で考えていたんですけど。戦争の映画を使うのはいろいろと技術的に困難だということが分かりまして、影と光と亀岡っていうセットにしました。あそこは視覚的なイメージをやりたかった。
Q:演劇界の裏側はリサーチされたりしたんですか?
監督:演劇界は全く知らなかったので、安田さんやエキストラに来ていた劇団の方にきいたりしました。
Q:映画と演劇、両方やっている演出家や役者もいますが、微妙にテリトリーが分かれていたりしますよね。
監督:ポンと演劇に飛び込んでいらっしゃる監督もいますし、逆に演出家として演劇をやられてて、ポンと映画監督をやられる方もいらっしゃいます。私は基本的に全く違うものだと思ってますので、まだ映画でいっぱいいっぱいです。
Q:横濱さんは今のところ、演劇の演出をしようとは思いませんか?
監督:思ってもないです。今回も本は読んだりしたんですけど、演劇の演出家は難しいというか、とっても緊張しました。
Q:カブで移動するシーンの背景をわざと合成のように見せているのはなぜですか?何か編集で思ったことがあるようでしたら教えてください。
監督:亀岡が最後に室谷へ向かうところで、スクリーンプロセスという技を使っています。昔からある映画の古典的特撮方法なんですが、この映画ってジャンルで言うとロードムービーとも言えますが、私はトリップムービーだなと考えていまして。
ロードムービーは色んな場所を転々と進んでいく中で物語が進んでいきますけど、この映画もその意味ではロードムービーです。ただ、亀岡の意識のトリップとか、夢を見たりとか、妄想をしたりとか、酒を飲むとか眠るとか、そういうことがよく出てきます。酒を飲んでも意識はトリップしますし、眠ることでもトリップしているという。そういうトリップムービーだと私は勝手に名づけました。また、映画の中でも現実と非現実が境界線がなく、ひょいっと突然現れる。現実を歩いている時に突然時制が未来になってしまって、全く別の場所に行ってしまう。そういう現実と非現実をトリップするという意味でも、トリップムービーだなと。なので、このスクリーンプロセスのシーンもあえて嘘をやってしまおうというか、この映画では実写で車を走らせてそれを撮影するということよりも、思い切って嘘を見せてしまうことが十分成立するなと思って、実際に使いました。実写で撮るより労力もかからないし、映画としても有効性があるということで。
Q:監督は6年ぶりの長編だと思いますが、それについて思うことはありますか?
監督:6年前はオリジナルで『ウルトラミラクルラブストーリー』を撮ったんですが、なかなか映画業界も変わってきまして、オリジナルで映画を作ることがそんなに簡単ではないという状況です。そんな中でも、自分のオリジナルの作品を何本か書いたり、別の原作もののお話があったりしつつ、しかしそれも制作までこぎつけるというのが至難の業でして。『亀岡拓次』という作品が実質初めての原作ものとなりました。
今までは自分自身の物語というか、私の内発的なところから生まれる物語をずっと書いてきました。今回は成井昭人さんという原作者の視点・世界観からの見方、それを私がバトンタッチして、また別のものにするという作業において、やはり今までやってきた自分の映画作りとは全然違う姿勢、モノの見方が必要だなとすごく思いました。
6年前は初めての長編映画でもあったので、本当に好きなようにやらせてもらった感じはあるんですが。今回はプロデューサーの意見ですとか、初めて合う安田顕さんのご意見ですとか、いろんな方の意見が沢山あって、それを汲みつついかに実現していくか、映画にしていくかという、そういう点では今までにしたことのない経験をさせてもらったなと思っています。
結局自分は自分でしかないんだなということを、映画を作り終わって思いました。結局自分に立ち返ってしまうというか。これからも原作とかオリジナルとかこだわらずに何でもやってみたいなと思います。
Q:原作はありますが、脚本は最初からご自分でやろうと思われたんですか?
監督:企画が立ち上がった2年前には別の脚本家に入ってもらってましたが、途中で私がバトンタッチしました。
Q:それは自分が書いたほうがやりやすいんですか?
監督:最初の脚本は男性が書いていて、やはり男性が主役の映画なので、その男性の視点というか、そういう点では影響が最後まで残ってると思います。でも、自分の分からない事は出来ないというか、私自身が消化しないとできない部分がかなり多いので、最後は自分でなんとか、自分が面白いと思うものをもっと脚本に取り込もうという感じで、最終的には自分で書きましたね。
Q:脚本の段階で安田さんの顔はあったというお話でしたけど。麻生久美子さんの方はどうですか?
監督:あずみという役が一度離婚して子供もいて、出戻ってきたという設定なんですけど。若い人じゃ駄目だなと思ってました。ちょうど30代もしくは40代始めのあたりの女優さんってそんなに多くいらっしゃらないので、以前仕事をさせていただいた麻生さんが最初から頭にありました。
麻生さんはすごく細かい芝居のコントロールが出来る方で。例えば「あと5グラムぐらい重く演技してください」と言うとしたら、それをそのまま忠実に、その5グラムという感覚は私と麻生さんとでしか共通じゃないかもしれませんが、それくらいの微調整が出来る。すごい技術力のある女優さんです。あずみという役は、長いひとつのシーンの中でも感情の変化が移ろっていくので、そういう微調整がちゃんと出来る役者さんで、かつ大人の女性、そして映画としてのヒロインという、全部を兼ね備えているという意味で、やっぱり麻生さんにやっていただいて本当に良かったと思います。
Q:インスピレーションとして安田さんが念頭にあったということですが、実際に仕事をしてみて安田さんについて感じたことはありますか?
監督:とてもシャイな方で、人が沢山いるところで本音をおっしゃらないというか、二人きりになって初めてポロっと核心を突いたことを言う。誰にでも明るく振舞うという感じではなく、いい意味での暗さをもった方だというのを撮影前にも思ったし、撮影中もそんな感じでしたね。
亀岡拓次ってつかみどころのない役なので、何か絶対譲れない強烈な性格はありません。その都度その都度、目の前にあることを一生懸命にやるっていうことしか安田さんには上手く演出できなかったんですけど、私が発するちょっと分かりにくい言葉にも応えようとしてくださったりしました。二人の間で完全に意思疎通がうまくいったわけではなく、お互いが分からないまま現場にずっと居続けたというか、居続けることが出来たというか、そういう感じでした。
現場中は、この亀岡拓次がどんな風に映画の中に存在するのか、私は想像できずに毎日撮影を続けていた感覚があるんですけど、編集をつなげた作品を観て、安田さんが持ってる凛とした華の部分、そして暗さの部分をよくこんなに出し惜しみなく全て出してくれたなと思っています。これまで全く見たことのない安田さんがいっぱい映っていて、そういう安田さんを出してくれてありがたいなと今は思っています。
最後に
監督:数ある映画の中で今日、この時間に亀岡拓次を選んでくださりありがとうございました。みなさんのお言葉によって映画が成長していく段階に今入っていますので、是非公開までに、皆さんの思われたことを何かに表現していただければと思っています。今日はありがとうございました。

©2015 TIFF
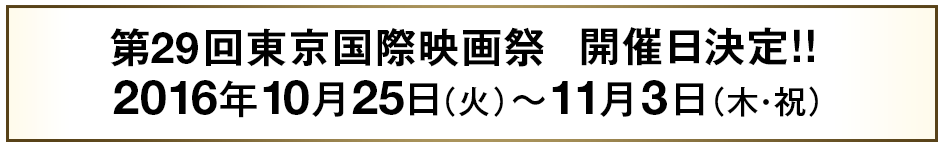
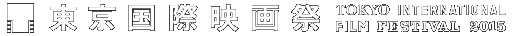


















 Check
Check






