10/28(水)コンペティション『モンスター・ウィズ・サウザン・ヘッズ』の上映後、ロドリゴ・プラ監督、サンディーノ・サラヴィア・ヴィナイさん(プロデューサー)をお迎えし、Q&Aが行われました。⇒作品詳細
ロドリゴ・プラ監督(以下、監督):こんばんは。このフェスティバルで僕の映画を観に来てくれて本当にありがとうございます。一緒の時間を過ごすことができて嬉しく思います。そしてこのような大きな部屋で、とてもたくさんの方で満員にしてくださったことにも嬉しく感じております。矢田部さんほか、フェスティバルの実行委員会の皆様にも感謝したいと思います。
サンディーノ・サラヴィア・ヴィナイさん(以下ヴィナイさん):コンバンハ。私たちの作品をコンペティション部門に招待してくださったことに感謝いたします。
Q:まず1問目は『モンスター・ウィズ・サウザン・ヘッズ』というタイトルの意味を監督にお聞きしたいと思います。
監督:この映画は、私の妻であり小説家であるラウラ・サントゥーロの書いた小説がベースになっていて、その小説のタイトルが『ア・モンスター・ウィズ・サウザン・ヘッズ・ウィズアウト・ブレイン』、つまり脳みそのない、千の頭を持ったモンスターというタイトルでした。このタイトルで何が言いたいのかといいますと、一つには大企業の体質というものを表しています。大企業であるがゆえに、いろいろな部門に分かれていて、それぞれの部門、担当者が誰も責任を取ろうとしないという体質、また倫理的な責任を誰も取りたがらないという会社の体質を表しています。
Q:公式パンフレットを拝見しますと、脚本というクレジットがなくて、監督のお言葉で小説に書いてストーリーを作っていったと書かれています。脚本は書かれなかったのですか?もし脚本なしで撮影を進められたのであれば、どういったかたちで撮影をされたのか、教えていただけますか?
監督:私の妻が書いた原作を元にしています。彼女は常に私と一緒に行動してくれて、原作を書きつつ脚本も書いてくれたり、演出にも一部関わっていて、とても重要な役割を担っているんです。彼女はいろいろな質問に答えてくれたりもしますし、私もその脚本の執筆に参加しています。その原作の小説の中ではいろいろな人達が一人称で出てきて、モノローグがたくさん使われています。それで脚本はあったのですが、まずは俳優さんたちと小説から発展させて、それぞれアドリブをしてもらいながらキャラクターの理解を深めてもらい、脚本に磨きをかけていくというような、そんなかたちで進めていったんです。
Q: 75分というのは最初からコンパクトな映画にしようと思われたのか、それとも結果的に作ってみたら75分だったのか、そこをおうかがいできますか?
監督:結果的に75分におさまりました。CEOのシークエンスは、撮っているうちにだんだんいい人になりすぎてしまって、ちょっとそのキャラクターはどうかと、もう少し別の人物像にしたかったので、一部カットした方がこのストーリーを伝えるうえでいいだろうということで、ああいうかたちにおさまりました。
Q:以前の『マリアの選択』という作品では、今作と同じように社会の絶望の淵に追いやられる女性を描きながらも、もっとゆったりとしたペースでしたが今作はどちらかというとジェットコースターのように観客を振り回すものになっています。そうした作風の転換にはどのような意図があったのでしょうか?
監督:たしかに前回の作品と比べると、ちょっとダークな部分はあったかと思います。ですが、このように映画を続けていると、撮っている瞬間の気持ちというのが反映されると思いますし、これまで自分が居心地がいいと思っていた場所から先に進んでいくものだと思っているので、新しいことも試していかなければなりません。ただ、新しく試している中で、過去の作品とも関連はしているものです。前回の作品は、父親と母親の二人の視点で固定されていて、映像もすべてその二人の視点で描かれていましたが、今回の作品ではそれを複数の人たちの視点として描き直しています。ですから視点という意味では前の作品を継承している部分もあるわけです。
Q:この映画は、軸の話がありながらも、同時にフラッシュバックになっているという構成が非常に特徴的だと思います。なかなかこういう語り方は観たことがないのですが、どのようにして思いつかれたのでしょうか?
監督:一部は小説の中にすでに組み込まれていた部分もあるのですが、映画としてはそれをさらに突き詰めようとしていました。というのも、ある一つの視点、たとえば主人公の視点だけでストーリーを作ってしまうと、それは私たち監督や脚本家の意見を押しつけることになってしまって、主人公とだけ共感してしまい、それ以外の共感の仕方がなくなってしまうと考えたんですね。ですが、この作品のようにいろいろな人たちの主観的な証言を組み合わせることによって、全体的なバランスがとれて、人によっては、あの女性は彼女を撃ったから嫌いというような意見も生まれてくるわけです。
Q:作品の中ではまったく音楽が使われていないのですが、それは何か理由があるのでしょうか?
監督:外部からの音楽を使うのはあまり好きではないんですね。というのも、それは観客の感情を誘導してしまうからです。この作品の場合は、我々は一歩下がって、観客がどのように感じるべきかといったことを映画の音楽で誘導するのはやめたかったんです。使ったとしても、すごく主観的に、手短かにちょっとだけ使うというかたちをとっています。
Q:お金持ちの株主の女性の映像がいつもピンボケですが、それは何か象徴しているんでしょうか?
監督:画像がぼやけている、ピントがブレているというのは、株主さんのキャラクターだけではなくて、ほかのキャラクターもそうなんですね。それはなぜかと言いますと、それぞれの人たちがその瞬間を思い出したときの記憶を再生しようとしていて、記憶というのはだいたいボヤっとしているものなので、それと同じように画像もボヤっと表現しています。
Q:奥様が書かれた小説というのは、日本語あるいは英語に訳されているのでしょうか?
監督:残念ながらメキシコとウルグアイでしか出版されていないので、もしこの中に出版社の方がいましたら是非ご検討ください。
Q:最後の曲はラモーンズですよね?
監督:オリジナルですが、ラモーンズ風です。
Q:途中で息子さんが「リアーナやジャスティン・ビーバーは聴くか?」と聞かれて、「いや、パンクやロックのほうが好きだ」と答えているシーンがあります。今の若い子が聴きそうな音楽ではなくて、あえて古い音楽を好きという設定にされたのはどうしてですか?
監督:今おっしゃっているのはキッチンの中のシーンなんですが、そこで話している相手の男性は、息子をからかっていながらも同情的でいい人だという風に観客には見てもらいたかったんですね。その上で、息子はバットで頭を殴ってしまいます。ロックやパンクが好きというのは、自分のお父さんが好きだったからということで、音楽もお父さんの趣味と一緒ということです。
Q:原作のタイトルから抜いた『ウィズアウト・ブレイン』の部分について、もう少し深くおうかがいできますか?
監督:「ブレイン」の部分なしでも充分タイトルが長いので、そのままでは長すぎると思ったというのもありますし、映画というのは、フレームに映らない余白というものがあります。余白を残すことによって、観た方がいろいろと想像して、どういうものかをそれぞれに感じることができる。タイトルを変えることで、皆さんがいろいろな視点を持って、いろいろな捉え方ができると思いました。オープンにしたかったんです。
最後に
ヴィナイさん:こんなにたくさんの方々にお越しいただき、ほぼ満席で、しかも最後までお付き合いをいただいて、大変嬉しく思っています。みなさんに楽しんでいただけたなら光栄です。ありがとうございました。
監督:このように日本で私の作品を上映できて嬉しいですし、光栄です。私は日本の文化が大好きで、川端康成や阿部公房の本を通して親しんでいますし、日本の監督さんも好きです。残りの滞在も楽しませていただこうと思います。ありがとうございました。
2015.11.13
[イベントレポート]
「映画には、フレームに映らない余白がある」コンペティション『モンスター・ウィズ・サウザン・ヘッズ』-10/28(水):Q&A
Tweet
左からロドリゴ・プラ監督、サンディーノ・サラヴィア・ヴィナイさん(プロデューサー)| ©2015 TIFF

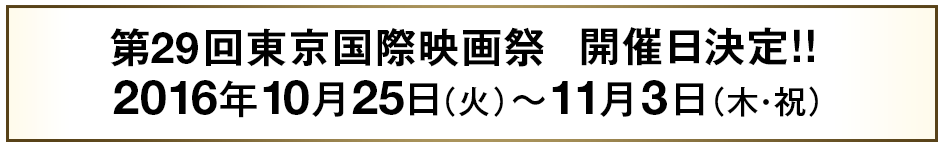
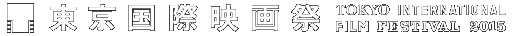


















 Check
Check






