©2015 TIFF
10/23(金)、コンペティション『ぼくの桃色の夢』の上映後、ハオ・ジエ監督、俳優バオ・ベイアルさん、女優スン・イーさんをお迎えし、Q&A が行われました。
⇒作品詳細
ハオ・ジエ監督(以下、監督):はじめまして!今回初めて東京国際映画祭に参加できて嬉しいです。大変光栄に思います。ありがとうございます。
スン・イーさん(以下、スンさん):こんばんは。ありがとうございます。今回初めてこの東京国際映画祭に参加させていただき、東京がとても好きになりました。本当に出会う人が優しくて、東京の風景もとても素敵です。
Q:主人公がやがて映画監督になるという物語でしたが、これは監督の自伝的な作品なのでしょうか?
監督:ほとんど自伝です。85%は僕の実際の経験に基づいています。
Q:3本目の作品で85%の自伝的作品を作ろうとした理由を教えてください。
監督:中国の改革・解放という大きな流れに沿って育ってきた少年が映画監督になる。それが僕の経験であり、リアルなストーリーなのですが、それはつまり底辺の庶民の目から見た社会なわけです。当時、改革・解放という流れの中で、高校の教育改革というものが盛り込まれました。そういうものが始まった時期だったんですね。すると今までは大学にいけなかったような農村の子供たちも大学にいけるようになり、だんだんと庶民の力が社会に大きく出てくるようになってきた。そういう時代なのです。なので、映画もその方向に向かって発展していきました。実は今まで、僕が観てきたような映画はそのあたりのストーリーを語ったものがなかったように思います。なので、僕は自分が実際に経験したことに基づいて、自分なりの映画、自分の目でしっかりと歩んできた道、そして世の中を見据えてみたいと思ったんです。
Q:彼女をとってしまう不良青年の名前が、ホーナンという『古惑仔(コワクチャイ)』でイーキン・チェンが演じていた役の名前なのですが、何か意味があるのでしょうか。それから『男たちの晩歌』みたいな音楽が流れたりとか、監督の香港映画のルーツをお聞かせいただきたいです。
監督:僕らが少年期から青年期を迎えた1990年代というのは中国の改革・解放が始まってまもなくの時期でした。そして外のものが、なかなか田舎にまで入ってこなかったのです。ビデオシアターという小さなものが町にあったんですが、そういうところで観られるのは香港の『欲望の街/古惑仔(コワクチャイ)I』とか、様々な香港ワールドのものが入ってきました。それが僕らの世代にとって初めての外との接触でした。こういう香港の作品は僕ら若者にとっては精神的なリーダーだったんです。そして僕らはそういう作品に、彼らに憧れて青春時代を過ごしていました。そういう時代でした。だから社会を反映するために、そういう物を取り入れています。
Q:前半はコメディータッチが強調されていましたが、後半になると社会問題の色が濃く反映されて、前後半で作品のテイストが大きく異なっていたと思います。どのようなお考えでそうなったのでしょうか。
監督:まずはとても幼い頃から始まって、中学校・高校、それから大学にいってからその後……というように、大体3つに区切られると思います。人生の経験の中でこの3つの部分というのは、人間みなそれぞれ色合いが違うと思います。なので、映画でも主人公の成長に伴って、テイストをかなり変えていきました。
Q:バオさんにお聞きします。セカンドパートからサードパートにかけて、コミカルな部分とシリアスな部分を演じわけるというのは難しかったのではないでしょうか。
バオ・ベイアルさん(以下、バオさん):この役を演じるには、いくつかの越えなければならない大きな壁がありました。1つ目は、今作には僕が今まで演じたことのないキスシーンやベッドシーンがありまして、まず演じる前に妻に許可をもらわなければなりませんでした。また、母親が撮影現場にいたものですから、そういう現場に我慢できるかという、環境的に大きな問題がありました。2つ目は、ハオ・ジエ監督の作品に出ている人たちはほとんどが素人だという点に難しさがありました。僕は北京電影学院で演技を学んで、ずっと演技をやっているプロです。そのプロの僕と、素人の方たちとの演技をどうやって合わせていくか。それが僕にとってはとても難しかった。学んできたものを消去していくような、消去法で演技を作ってくということをしなければなりませんでした。
Q:スン・イーさんも難しい役だったと思います。演技をされていかがでしたか?
スンさん:私は、この映画の中で3つのパートを演じています。小学校から中学校、高校の辺りは、演じるのはそんなに難しくありませんでした。やっぱり年齢的に近いので、どちらかというと演じやすかったです。私が難しいと思ったのは、大人になってから、特に妊娠してからのあたりです。もちろん私はそういうことを経験したことがないので、彼女の心理状態を掴むのがとても難しかったですね。役と同じくらいの年齢の方たちを一生懸命観察したり、いろんな方とお話をしたりして、このサードパートの役作りをしていきました。
Q:作中に映画『マレーナ』が流れるシーンがありました。影響された部分があるのでしょうか。
監督:この『マレーナ』はヨーロッパでは普通の映画だと思いますが、中国では独特な雰囲気があります。当時の、抑圧された想いを抱えた若者たちにとてもうけた特別な映画なんです。僕が大学に入ったころは、「健康のために自慰行為は自粛しましょう」というようなことがラジオでもよく言われていました。それくらい性を抑圧するような雰囲気だったわけです。青春の真っ只中の、ちょうど成長期にある青年たちが性を抑圧されて、性というのは徹底的に否定されるべきものだったんです。なので、そういうことを考えるだけでダメだと、それはとても恥ずかしいことだというふうに思っていたわけです。僕らは本当にそういう風に思い込まされていました。でも『マレーナ』を観て、これでいいんだと思いました。僕はこの映画からとても大きな勇気をもらったんです。
Q:最後に監督から一言お願いします。
監督:バオ・ベイアルさんにお願いしましょう。この映画の中で彼は「僕」ですから。
バオさん:クランクインの初日のことなんですが、監督が国旗を掲揚するポールに登って、拡声器でスタッフ、役者、全員の前でこう言いました。「僕を信じてくれ!僕はこの映画をちゃんと撮れなければ命を投げ出す、死んでもいい」と。でも、この完成した映画を観ると監督は死ぬ必要はないですね。ハオ・ジエ監督は命がけでこの作品を撮ったんだと思います。僕らもこれから映画というものに命がけで取り組んでいきたいと思います。
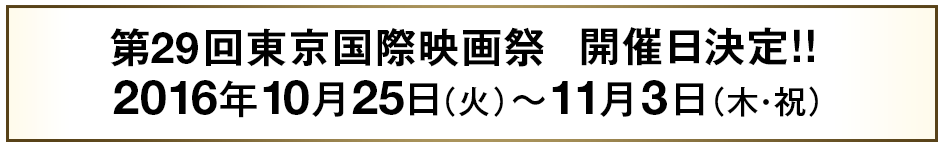
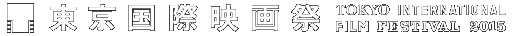


















 Check
Check







